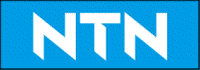コースの安全管理

フランスで開催されている世界最大の自転車ロードレース「ツール・ド・フランス」の山岳コースに於いて、総合優勝争いを繰り広げている選手たちが、観客が殺到するエリアで足止めを食らってしまうという悩ましい事故が発生しました。
詳しい状況を説明しますと…
「モン・ヴァントゥ」という注目の上級山岳ステージの山頂フィニッシュエリアで、「時速100km/h」という強烈な風が吹き荒れていたことから、主催者はフィニッシュ地点を6km下げるという特別処置をステージ前日に決めました。
その後、注目の「モン・ヴァントゥ」ステージの観戦を楽しみに世界中から集っていた観客が、全長が短くなった山岳コース上にギュウギュウに押しかけて、更に何らかの理由でコースフェンスの設置区間が通常よりも短いものとなり、その結果、カメラモトが観客と接触(もしくは接触を回避するために)してストップ。そこに、アタックを仕掛けて飛び出していた優勝候補3名が突っ込むという、衝撃的なアクシデントが発生してしまいます。
衝撃映像はこれだけでは終わらず、メイン集団の後ろから上がっていったカメラモトが捉えたのは、マイヨ・ジョーヌ(総合トップの選手が着る栄光の黄色いジャージ)を着たクリストファー・フルーム選手(チーム・スカイ)が、自転車に乗らず、また、彼の自転車の影も形ない状況で、普通に足で走っている(ランニング状態)という前代未聞の状況でした。
テレビを観ている我々も状況を把握するのに時間がかかり、しばらくしてようやく「カメラモトに突っ込んだフルーム選手の自転車を後続の別のモトが踏んで壊してしまい、観客の多さから後ろから上がってこれないチームカーを待つことなくとっさの自分の判断でフルームが壊れた自分の自転車を捨ててランニングでゴールを目指しはじめた」ということがわかりました。
その後、フルーム選手は、ニュートラルサービスから受け取ったサイズの合っていない自転車に一旦乗り、そして、ようやく観客をかき分けて上がってきた自チームのチームカーから自分のスペア自転車を受け取って再びゴールを目指しました。
この結果、フルーム選手は、転倒時に一緒に走っていたライバルから1分40秒遅れでゴール。個人総合時間順位もその時点での1位から7位まで転落してしまいます。
結果的には救済処置が適用され、フルーム選手は総合首位をキープ。各チームや選手たちからも「レースボイコット」の様な大きなクレームは発生せずに、レース主催者のASOはなんとかこのアクシデントをうまく切り抜けることに成功しました。
今回の事故で改めて感じたことというのは、「観客数の増加=大会の成功」という単純な発想のみで自転車ロードレースを考えてはいけないということです。
大自然をスポーツフィールドに変えてレースを開催する自転車ロードレースというスポーツは、基本的に入場料をとれないスポーツであり、むしろ「観客数の増加=警備費用などの増大」に繋がり、ビジネス的な観点で言えば、観客が増えれば増えるほど財政面が圧迫されていくことに繋がるリスクがあります。
また、入場制限などについても、そもそもクローズドされていないオープンエリアでレースを開催していることから、それ自体に想像を超える労力と費用がかかってしまいます。
(かつて国内でも有料観戦エリアという発想でお客さんから入場料をいただく試みを実施したレースがありましたが、結局のところ有料エリアを設けることと、それらを管理する体制を構築する費用がかさみ、結局、プラマイ・マイナスとなってしまったという事例があります…)
(かつて国内でも有料観戦エリアという発想でお客さんから入場料をいただく試みを実施したレースがありましたが、結局のところ有料エリアを設けることと、それらを管理する体制を構築する費用がかさみ、結局、プラマイ・マイナスとなってしまったという事例があります…)
ASOの様にビジネスとしてやっていける数少ないレース主催者であれば、こういった不測の事態や対策などにも忍耐強く向き合っていくことはできるでしょうが、一方で、ジリ貧でギリギリの財務状況で運営を続けているレースなどについては、一度のミスで大会自体を吹き飛ばしてしまうことも十分にあり得ます。
かつて、日本のレースは「安全面の確保やレース運営に労力をかけたくない」という理由から、「コース上からお客さんを締め出す文化」が主流となっていました。しかし、最近になってようやくヨーロッパの様な「お客さんを大切にする文化」が根付きはじめてきています。
ただし、闇雲に「観客数の増大」を追い求めていっては、いつか今回の「ツール・ド・フランス」での事故と同様のアクシデントが発生するリスクもあるのでしょう。
レース主催者として、世界のレースで起きている様々な事象にアンテナを張り巡らせることは重要な作業といえます。
常に大き目の視野を持ちながら、引き続き「ツアー・オブ・ジャパン」と「自転車」の未来を模索していきたいと思います。

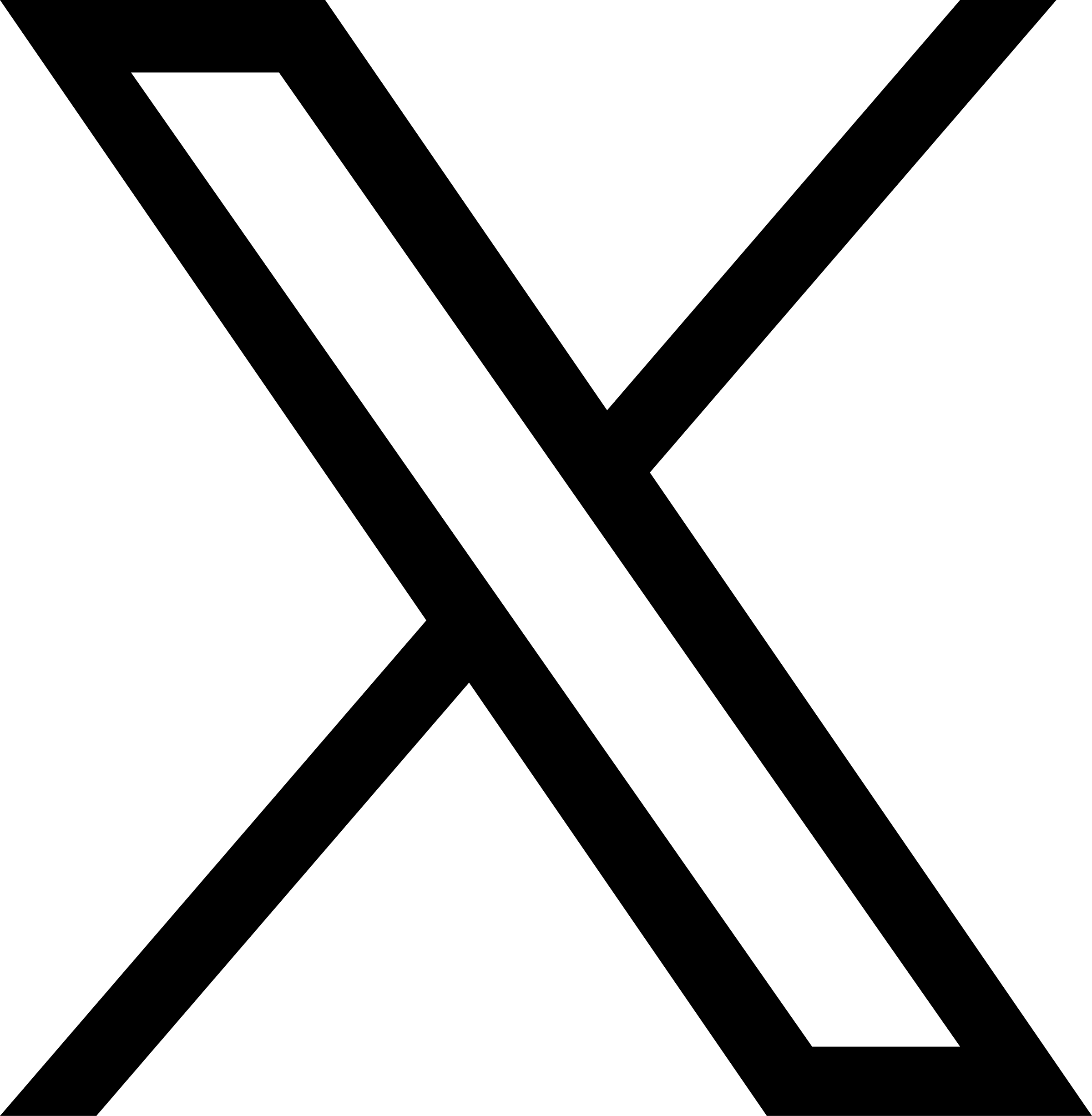
 ミニ 1:10 合金モデル 自転車ダイキャストメタルフィンガーマウンテンバイクレトロな自転車 大人の収集価値のある子供のおもちゃ、スタイル 2 赤
ミニ 1:10 合金モデル 自転車ダイキャストメタルフィンガーマウンテンバイクレトロな自転車 大人の収集価値のある子供のおもちゃ、スタイル 2 赤 「組立動画あり」【スピードワールド】ロードバイク 700*28C ドロップハンドル デュアルピボットキャリパーブレーキ 14段変速 軽量 自転車 補助ブレーキ搭載 オシャレ 通勤 通学 大人 男性 女性 学生 (ホワイト)
「組立動画あり」【スピードワールド】ロードバイク 700*28C ドロップハンドル デュアルピボットキャリパーブレーキ 14段変速 軽量 自転車 補助ブレーキ搭載 オシャレ 通勤 通学 大人 男性 女性 学生 (ホワイト) PEWETE 全12カラー 1/10スケール 自転車玩具 ダイキャストバイクモデル, 黒#1
PEWETE 全12カラー 1/10スケール 自転車玩具 ダイキャストバイクモデル, 黒#1 PANP RIDE CYCLE 空気入れ 自転車 ロードバイク 携帯 日本 メーカー (全バルブ対応) 米式 英式 仏式 ボール 電動空気入れ 自動 軽量 小型 コンパクト エアコンプレッサー KUKIIRE スマート空気入れ【保証1年間】
PANP RIDE CYCLE 空気入れ 自転車 ロードバイク 携帯 日本 メーカー (全バルブ対応) 米式 英式 仏式 ボール 電動空気入れ 自動 軽量 小型 コンパクト エアコンプレッサー KUKIIRE スマート空気入れ【保証1年間】 YUHAFO 自転車 空気入れ 電動 くうきいれ 車 2025技术革新 6000mAh大容量電池 最大圧力150PSI 充電式 英式 仏式 米式バルブ対応 バイク オートバイ ママチャリ ボール用 LEDライト 自動停止 空気圧指定可 エアコンプレッサー タイヤ エアーポンプ コンパクトくうき入れ 収納袋 小型軽量携帯可 日本語説明書付き
YUHAFO 自転車 空気入れ 電動 くうきいれ 車 2025技术革新 6000mAh大容量電池 最大圧力150PSI 充電式 英式 仏式 米式バルブ対応 バイク オートバイ ママチャリ ボール用 LEDライト 自動停止 空気圧指定可 エアコンプレッサー タイヤ エアーポンプ コンパクトくうき入れ 収納袋 小型軽量携帯可 日本語説明書付き




![[ピクシーパーティ] サイクル パンツ インナーパンツ サイクリングパンツ お尻 痛み軽減 衝撃吸収 自転車 クロスバイク ロードバイク サドル 痛くない 分厚い ゲルクッション ゲルパッド メンズ レディース 夏 (XXXL, ブルー) 誕生日 プレゼント](https://m.media-amazon.com/images/I/51bewyFH-2L._SL160_.jpg)